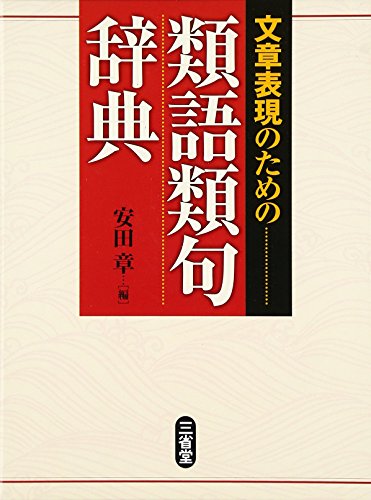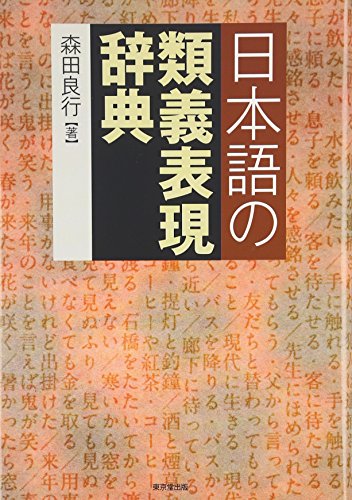(2021/04/20加筆)
ご存じのように、日本語の「類語辞典」にはいくつか種類があります。専門用語はあるのかもしれませんが、以下、帽子屋流に勝手に3つに分類してみました。
- 列挙式。説明なしに、類語や関連をただ羅列するタイプ
- 説明式。語句の細かい意味・用法を説明し、違いを示すタイプ
- 詳細説明式。語感、語法、違いを2. よりさらに細かく説明するタイプ
1. に該当するのが(以下、順序には特に意味なし)、
- 大修館『日本語シソーラス 類語検索辞典』
- 東京堂出版『逆引き同類語辞典』
- 三省堂『現代語古語 類語辞典』
- バリューネットワークス『デジタル類語辞典』
などです。2. の代表が、
- 小学館『使い方の分かる類語例解辞典』
- 講談社『類語辞典』
- 角川『類語新辞典』
- 三省堂『類語新辞典』
- 三省堂『新明解類語辞典』
- 三省堂『文章表現のための 類語類句辞典』
- 研究社『類義語使い分け辞典』
など。そして3.に当たる(と帽子屋が勝手に分類した)タイプとして
- 岩波『日本語 語感の辞典』
- 東京堂出版『表現類語辞典』
- 東京堂出版『日本語の類義表現辞典』
- 三省堂『類語ニュアンス辞典』
などがあります。
それぞれ、私がよく使っている辞書を中心に、簡単にまとめてみました。
●『日本語大シソーラス 類語検索辞典』(大修館書店)
●『日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版』(大修館書店)
列挙式でよく使っている辞書のひとつです(第2版になって、"大"がとれたんですね。今まで気づいてなかった……)。旧版、新版ともLogoVista版を使っています*1

日本語シソーラス 類語検索辞典 第2版(LogoVista)
新版では、掲載されている類語すべてにリンクが設定されたので、思いつくまま次々とリンクをたどっていけます。なかなか便利になりました。

言うまでもなく、類語の違いを調べるのではなく、並んでいる類語と、そこから刺激された自分の語彙のなかからぴったりの言葉を探すための辞典です。
●『逆引き同類語辞典』(東京堂出版)
東京堂出版から出ているユニークな辞書のひとつで、古本で見つけました。これについては旧ブログに記事があります(書いたのを、自分でも忘れてましたが)。
禿頭帽子屋の独語妄言 side A: # 『逆引き 同類語辞典』
●『現代語古語 類語辞典』(三省堂)
これも類書のない辞典です(書籍のみ)。
現代語も古語もいっしょにして類語として扱ってあるので、他の類語辞典とは違ったヒントが得られます。

古風な言いまわしを探すときに特に便利ですし(産業系の翻訳では、あまりない場面かも)、逆に新しい言い方の手がかりにもなります。列挙式に挙げましたが、コロケーションを示す簡単な例文も示されていたりします。
ちなみに、この辞典は芹生公男さんという個人の方が作ったもので、そのときの経緯を
『稼ぎもせんと二十年 ー辞典作り一筋ー』
というエッセイにまとめていらっしゃいます(Kindle版で読めます)。
さて、2.のグループに移ります。ひとつで済むことは少ないので、たいていは複数の類語辞典を渡り歩いています。
●『使い方の分かる類語例解辞典』(小学館)
個人的にいちばんよく使っている類語辞典です。
現在は書籍版しかありません*2が、お持ちでない方はgoo辞書に収録されている無料版が利用できます。

「使い分け」の説明が詳しいうえに、マトリックス方式でコロケーションも確認できます。
●『類語辞典』(講談社)
説明は『使い方の分かる類語例解辞典』ほど詳しくないのですが、使用頻度は次くらいかも(書籍のみ)。
収録語数が多く、語句あたりの語釈はほぼ均一の文字数で載っているので、「国語辞典としても使える」という特長があります。個人的には、類語グループを俯瞰的に捉え、特定の語句の位置付けを知りたいときに重宝しています。
●『類語新辞典』(三省堂)
カテゴリーのなかで類語の違いを調べたいときは、こちらもよく頼っています。
ただし、上のリンクは書籍ですが、私がふだん使っているのは iOSアプリ版です(書籍版は、今のところ持っていません)。
こいつのインターフェースがなかなかユニークで楽しいのです。

語句はカテゴリー分けされていますが、もちろん検索フィールドから検索できます。
検索した語が表示された状態で、下の欄を左右にスワイプすれば類義語を次々と確認でき、これは、と思う語があったら長押しすると、上の図の「親交」「高誼」「懇親」のようにクリップしておくことができます。
また、上の図で選ばれているのは、
[人間]→[活動]→[行為]→[交際・交渉]→[知り合う]
というグループの類語なわけですが、たとえば[知り合う]の行をスワイプして[修交]とか[心が通う]に切り替えると、ややグループの違う観点を見られます。これ、同じことを書籍上でやろうと思ったらけっこう面倒なので、アプリとしてはなかなか傑作だと思っています。私にとっては、物書堂アプリ以外で使用頻度の高い辞書アプリのひとつです。
●『新明解類語辞典』(三省堂)
※載せ忘れてたので追記しました。
上の『類語新辞典』をアプリで使うのと同じくらいよく使っているのがこれです(書籍のみ)。
それもそのはずで、この『新明解類語辞典』は、 『類語新辞典』をベースに、見やすく整理して作られた辞書なのです。
見やすさは、上掲の講談社『類語辞典』より良く(活字の大きさもある)、一覧性がとても高いので、類語グループを眺めながら言葉を選ぶ、あるいは手がかりにするときは、これに手が伸びる頻度が高いかもしれません。簡単な用例も付いているので、コロケーションの確認にもなります。
●『文章表現のための 類語類句辞典』(三省堂)
名前が示しているとおり、用例で使い方を示すというアプローチを試みた類語辞典です(書籍のみ)。
巻頭の「この辞書の構成」にはこう書かれています。
見出し語は、「文章表現のため」という観点から、必要と思われることばを選定した。すなわち、個個の物と対応する「物の名」は必要最小限にとどめ、意味概念を表す「ことば」を重点的に取り上げた。
単に類語の候補を探すのではなく、用例別に類語の使い方をつかんだうえで言い換えを探すという使い方ができます。
最後の3.のグループ、実は類書がもっとたくさんあります。
全般的な特徴として、収録語数を抑え、ひとつひとつの項目について深く掘り下げているものが多いグループです。また、個人が編纂したものも多く、人によっては「個人的な解釈が過ぎる」と思われる可能性もあります。
●『日本語 語感の辞典』(岩波書店、中村明)
個人編纂の類語辞典を代表する一冊。といっても、個人の見解が過ぎると感じることは、少なくとも私はあまりなく、語感の説明にたびたび助けられています(書籍のみ)。
たとえば、「日々」の項にはこうあります。
来る日も来る日も毎日という意味で、やや改まった会話や文章に用いられる。いくぶん古風でいくらか美化した感じのやわらかい和語。
こういった感じです(赤字は引用者)。さらに、用例ではコロケーションも示され、それとは別に実例を載せたうえで(近現代の文学作品が中心。「日々」の項目で引かれているのは正宗白鳥)、こう続きます。
どの日も欠かさずすべてというニュアンスのある「毎日」ほど厳密ではなく、「日頃」「日常」に近い緩やかな限定で使う傾向がある。「毎日」に比べ、一日ずつというより普段の日をまとめてとらえた感じが強く、「酒びたりの―が続く」「楽しい―を過ごす」のように一定の範囲の何日かをさす用法もある。
とても分かりやすいと思いません?
●『表現類語辞典』(東京堂出版)
図表や記号類をまったく用いず、文章だけで押し切ります(書籍のみ)。
『語感の辞典』と似たアプローチの辞典です。作例のほかは、やはり近現代の文学作品からの実例が多く引用されています。
「ちかごろ」という主見出しの下に「最近・近来・近時・昨今・近年」と並ぶ項などに助けられました。一部だけ引用します。
近年〔名・副〕〈最近〉よりも時間的な幅がかなり長い。この数年。かなり改まった言い方。
また、「ときどき」という主見出しにある「折折」についても、
〈ときどき〉とほぼ同義だが、やや改まった古風な言い方。
とあります。こういう「改まった」とか「古風な」という分類が、どの国語辞典を引いても必ずラベルとして付いていればいいのですが、残念ながらそうではないので、こういう記述が役に立ちます。
ちなみに、私がこういう類語の違いを調べるのは、たいてい英日翻訳の答案を採点しているときです。たとえば答案で「近年」という語が使われいて、そこにちょっとズレを感じたとき、そのズレが自分ひとりの語感ではないという裏づけがほしい。そういう使い方をしています。
●『類語ニュアンス辞典』(三省堂、中村明)
『語感の辞典』と同じ中村明氏の労作。同氏が編纂に当たった『新明解類語辞典』(三省堂)のいわば副本として作られた辞典です(書籍のみ)。
巻頭にある「この辞典の位置と性格」にこう記されています。
(新明解類語辞典)それぞれの単語の意味は、むろん本文中で説明してあるが、収録語数が延べ五七〇〇〇語の項目にも及ぶと、細かい意味の違いや微妙な語感の差まではなかなか手が届かない。そこで本辞典の登場となる。そういう紛らわしい語群のそれぞれの意味や語感の違いと、たがいの使い分けに焦点をあてて、ことばのニュアンスをわかりやすく解き明かすのが、この本の目的である。
個人的には『語感の辞典』よりますます個人の主観が入った、極論しちゃうと中村氏による "類語エッセイ" と言えなくもない一冊ではないかと思っています。辞典というより読み物です。「無礼」の説明はこう始まります。
「無礼」という語には身分不相応というニュアンスが感じられる。士農工商と身分がはっきりしていた江戸時代には、「無礼者」とか「無礼な振る舞い」とかで、武士の面目を汚したと無礼討ちになる例があったらしく、そんなシーンを時代劇でたびたび目にする、小沼丹の『タロオ』に~
こうですからね^^; なかなか楽しい。
●『日本語の類義表現辞典』(東京堂出版)
こちらも個人による類語辞典で、著者は『基礎日本語辞典』 や『動詞・形容詞・副詞の事典』などで知られる森田良行氏です(書籍のみ)。
ただし、こちらは取り上げられているのが61語で、やはり辞書というより読み物。また、著者が森田氏だけあって、中村氏のように「語感」「ニュアンス」を語るのではなく、語法を軸に説明が展開されます。
私がこの本を買ったのは、第1項が
「練習する」か「練習をする 」か
だったからです。
以上、私の本棚に並んでいる書籍を中心に、日本語の類語辞典をご紹介しました。
もちろん、類語辞典ではなく国語辞典でも類語は調べられます。その話は、また次の機会に。